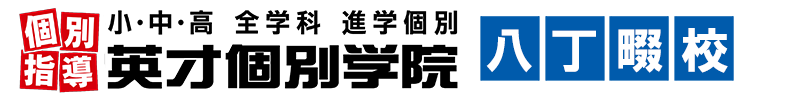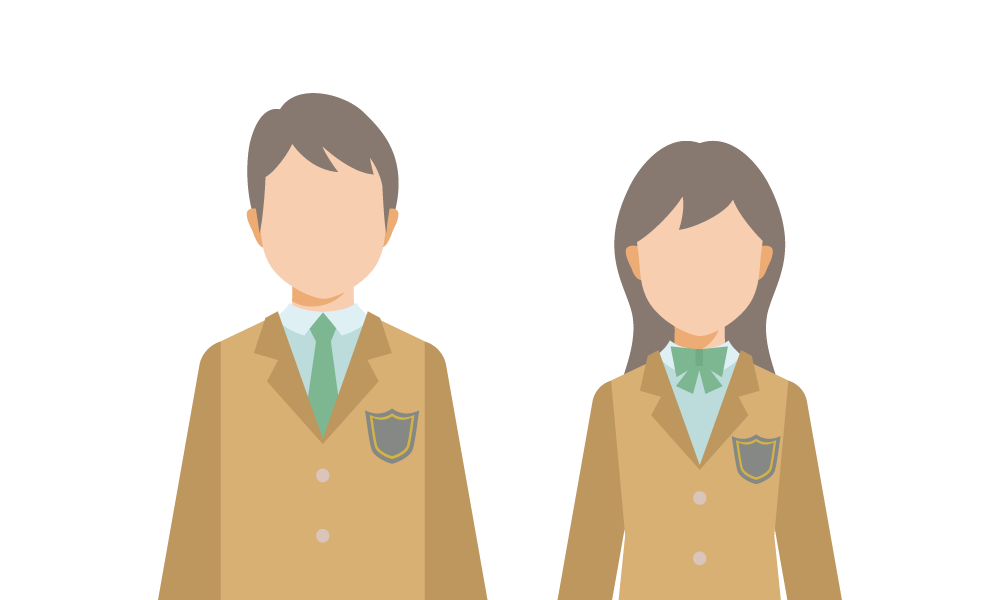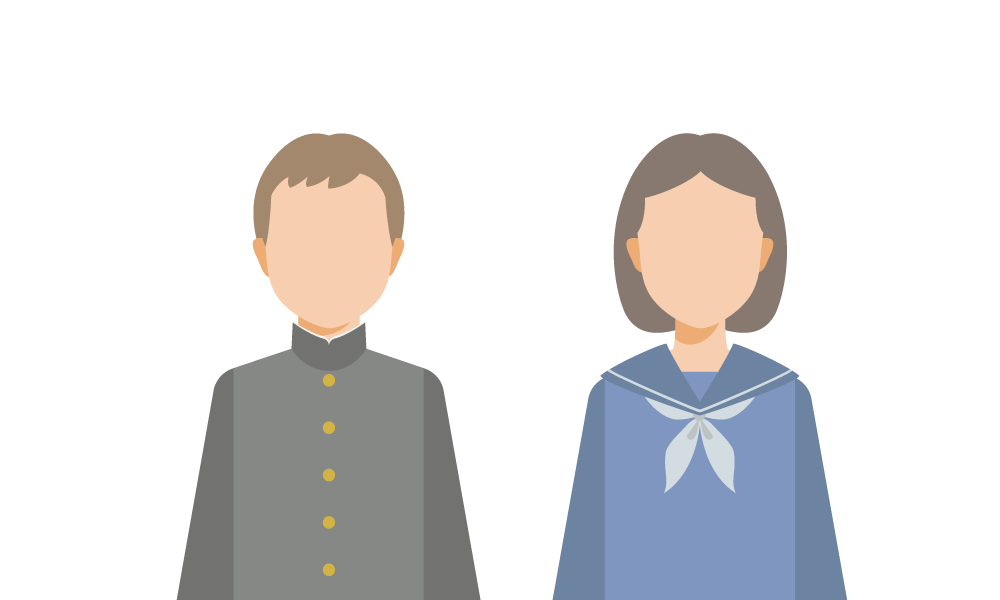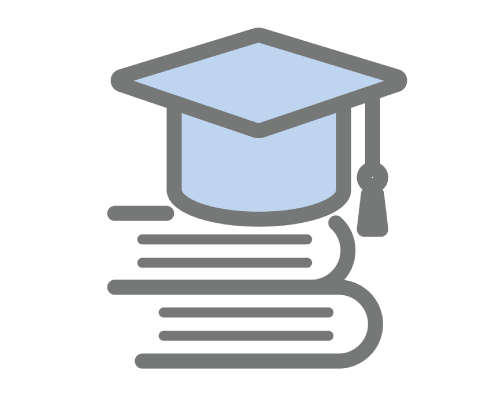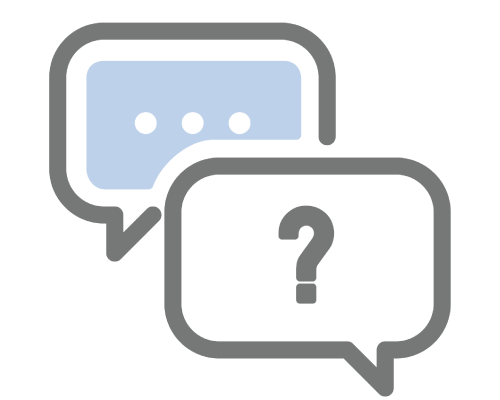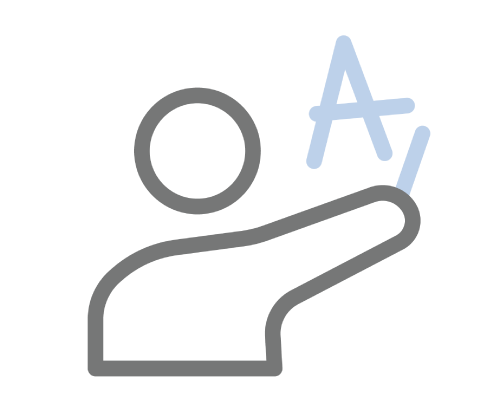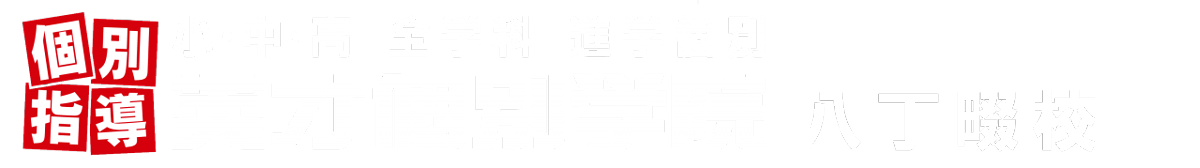ナンデモ解決!勉強ブログ
2025.10.13
【中3理科】天体は中学理科のラスボス!?
こんにちは!
英才個別学院 八丁畷校 室長の池田です☀️
今日は、中学理科の中でも「最後に登場するラスボス」――
そう、中3理科の天体分野についてお話します。
🌌 まずはこの単元一覧をチェック!
細かく見ればたくさんありますが、
実は下記の範囲をしっかり押さえれば、中3天体は十分対応できます!
🔭 中3理科・天体分野の単元一覧
-
銀河と銀河系・太陽系の違い
-
太陽系の惑星
-
太陽の特徴(質量・エネルギーなど)
-
黒点の観察と計算
-
天球の意味と見方
-
季節と太陽の動き
-
地域ごとの太陽の動き(北極・赤道など)
-
天球上の計算問題(3つの工夫)
-
南中高度の計算と意味
-
日影の長さ・日影曲線の動き方
-
星の日周運動と年周運動
-
星の位置計算(星の動きを計算する問題)
-
星の方角を求める問題(星の角度)
-
太陽の年周運動(西から東へ動く理由)
-
月の満ち欠けと見え方
-
月が西から東へ動く理由
-
金星の満ち欠けと見え方
-
西か東か問題(星や太陽の動きの方向まとめ)
これらを理解し、基本問題を数回演習しておけば、
模試や入試で出ても十分対応可能です。
(逆に、これ以上“深追い”する必要はありません!)
🧠 なぜ「天体」はラスボスなのか?
理由はいくつかあります。
-
イメージがしづらい
-
スケールが大きすぎる(地球の動き・太陽・星・宇宙…)
-
空間把握能力が求められる
-
南半球と北半球で向きが逆になる
-
計算問題が意外と多い
これらが重なって、
「理科の中で一番難しい…」と感じる生徒が多いんです。
🪐 出題されにくい理由
実際に過去3年間の模試をすべて確認しましたが、
天体分野の出題は極端に少ないのが現実です。
中学3年間分の模試で見ても、
-
大問:約6題
-
小問:約25問
しか出題されていません。
しかも、天体は中学理科の「最後の単元」にあたるため、
模試の作成時期には授業が終わっていない学校も多く、
そもそも問題が作られないケースが多いのです。
☀️ 出題されない=やらなくていい?
そうではありません。
**「出ることもある」**からこそ、
最低限の基礎だけは押さえておく必要があります。
ただし、入試や模試では
・作図問題
・観察記録問題
といった内容はほぼ出題されません。
つまり、
「暗記+基礎計算」だけでも十分対応できるのです。
🎓 教えられる先生が少ない理由
実は、この分野をしっかり教えられる先生は多くありません。
理系出身でも「地学専攻」という人がほとんどいないからです。
大学で地学を専門に学べる学科は非常に少なく、
高校でも「地学基礎」や「地学」を開講している学校はほぼありません。
(大学入試で利用する生徒がほぼいないのが理由です)
実際、私・池田自身も大学探しの際に「地学を学べる学科」を探しましたが、
全国的に見ても本当に数が限られていました。
💡 結論:深追いは不要。でも基礎は押さえよう!
天体範囲は確かに難しく、
理科の平均点を下げやすい単元です。
だからこそ、
「深追いせず、基礎をしっかり理解する」
この姿勢が一番効率的です。
出題されなくても、
「なんとなくはわかる」レベルまで仕上げておけば十分です。
📚 英才個別学院 八丁畷校では、
この“中学理科のラスボス”ともいえる天体分野を、
図やアニメーション、模型などを使って 感覚的に理解できる授業 を行っています。
理科が苦手な生徒でも、
「なるほど!」「イメージできた!」と
スッと腑に落ちるようにサポートしています🌟
📞体験授業・ご相談はお気軽にどうぞ!
LINE・HP・お電話(044-230-0039)から受付中です。