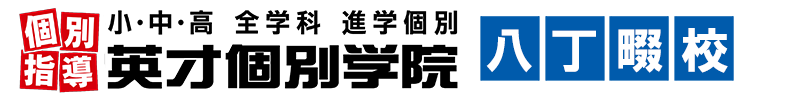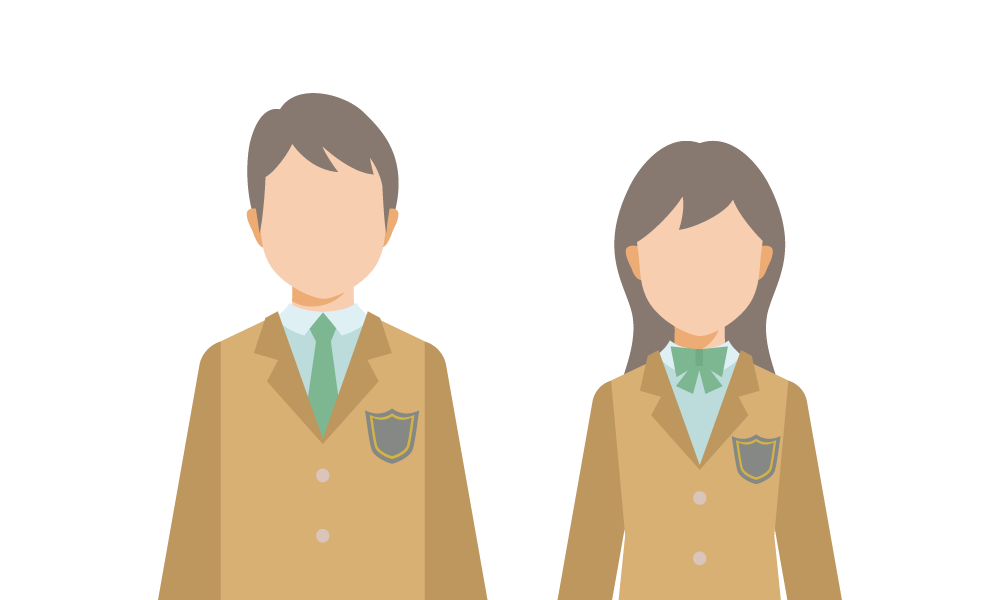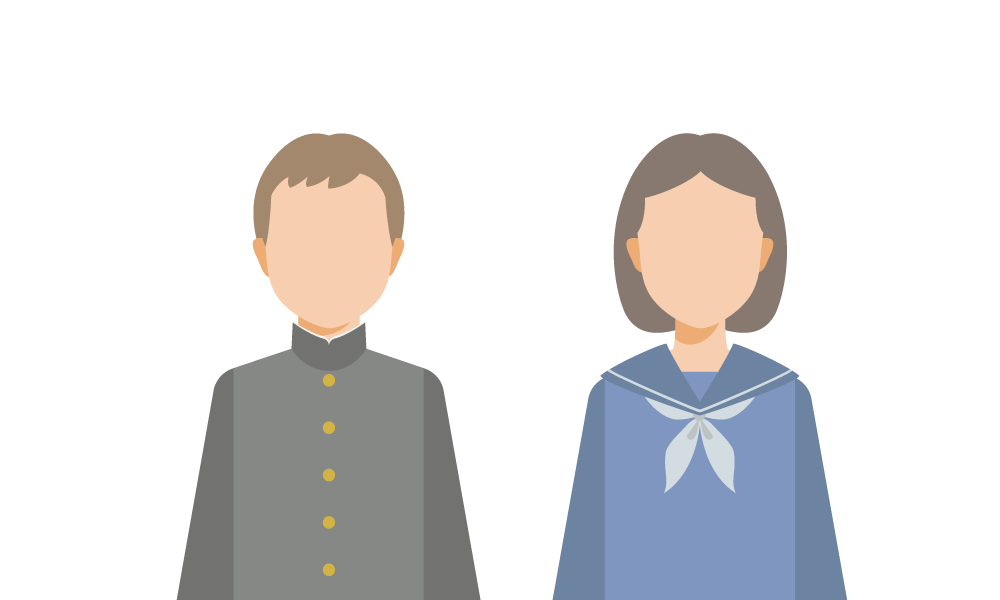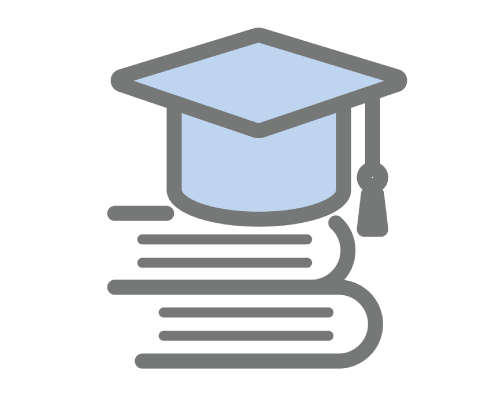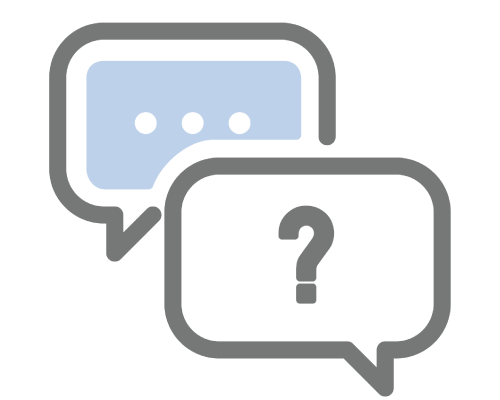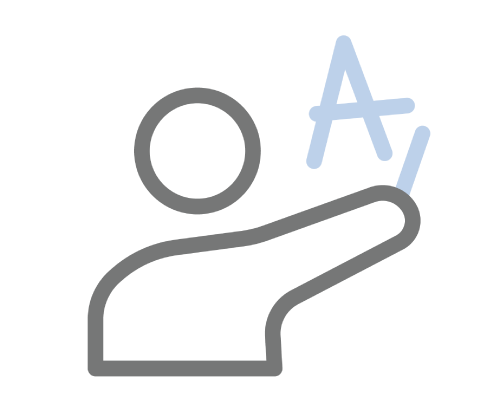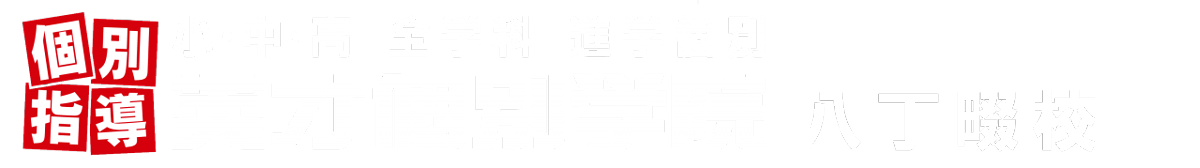ナンデモ解決!勉強ブログ
2025.10.05
【中学受験】過去問は“ラスボス”じゃない!──逆転合格への正しい使い方とは?
こんにちは!
英才個別学院 八丁畷校 室長の池田です。
中学受験を控える皆さん、そして保護者の皆さま。
この時期、「過去問、いつからやるべき?」「どのくらい解けばいいの?」という質問を多くいただきます。
そこで今回は、**“過去問の神”と呼ばれる後藤和浩さん(声の教育社)**の講演内容から、
「逆転合格につながる過去問の使い方」を分かりやすくご紹介します!
🎯過去問は「ラスボス」ではなく「成長ツール」
「過去問は最後に取っておくもの」「先に解くと覚えてしまう」
そんな考え、実はもったいないんです。
後藤さんはこう語っています。
「過去問は倒す相手ではなく、成長のための最強の教材です。」
最新年度の問題からどんどん使ってOK!
なぜなら、最新の形式が来年の入試に一番近いからです。
「今年の問題はもう出ない」と考え、安心して取り組みましょう。
📘過去問の“横使い”で傾向をつかむ!
1年分ずつ解くよりも、年度を横に並べて見るのがポイントです。
たとえば、
「この学校は毎年“単位換算の逆算問題”が出ている」
など、出題者のクセが見えてきます。
これがわかると、対策の精度が一気に上がります✨
つまり、過去問は“解く”だけでなく、“分析して使う”ものなんです。
🗂️付箋で管理!達成感を「見える化」
後藤さんおすすめの方法がこちら👇
-
解けなかった問題に付箋を貼る
-
2周目でできたら付箋を取る
付箋が減っていくほど、自信と達成感が目に見えて増える!
「やり切った!」という実感が、最後まで走り抜ける力になります💪
🧠満点はいらない!狙うは“6〜7割”
合格者平均点を取る必要はありません。
学校は「受験者平均6割・合格者7割」になるように作問しています。
つまり、3問に1問は解けなくても大丈夫!
むしろ、その時間で解ける問題を完璧にする方が合格に近づきます。
🧩効果的な進め方のコツ
-
最新年度から解く
-
苦手分野を重点的に分析(例:立体切断・記述)
-
科目ごとの順番を決め打ち
-
国語:知識問題(漢字・語句)から
-
理科:大問1=生物 など固定傾向を活用
-
-
4教科一気にやらず、分けて実施
-
やりっぱなしNG!必ず見直し&分析まで
👪親の言葉が“合格後”を決める
講演の最後に、後藤さんが語った印象的な言葉があります。
「どこの学校に行っても、入った学校が一番いい学校です。
『この学校に入ってくれてありがとう』と、ぜひ伝えてください。」
中学受験はゴールではなく「スタート」。
入学後の6年間を気持ちよくスタートできるように、
お子さんの頑張りを認める言葉が何よりのエールになります🌸
✨まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 過去問はラスボスではなく味方! | 最新年度からどんどん解こう |
| 横に見て傾向を分析 | 出題者のクセをつかむ |
| 付箋で可視化 | “できるようになった”を実感 |
| 満点不要 | 6〜7割で十分合格圏内 |
| 親の声かけが大切 | 「ここに入ってくれてありがとう」で締めくくる |
中学受験は、「点数」だけでなく「成長」も試される挑戦です。
過去問を通じて、「できなかった」が「できた」に変わる瞬間を、
一緒に積み上げていきましょう!
忘れていなければ、
近々、中学入試の併願スケジュールについても
言及していこいうかと思います!
📞 お問い合わせ・体験授業は
LINE・HP・お電話(044-230-0039) からお気軽にどうぞ!