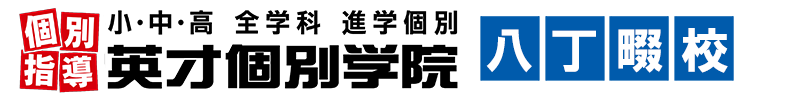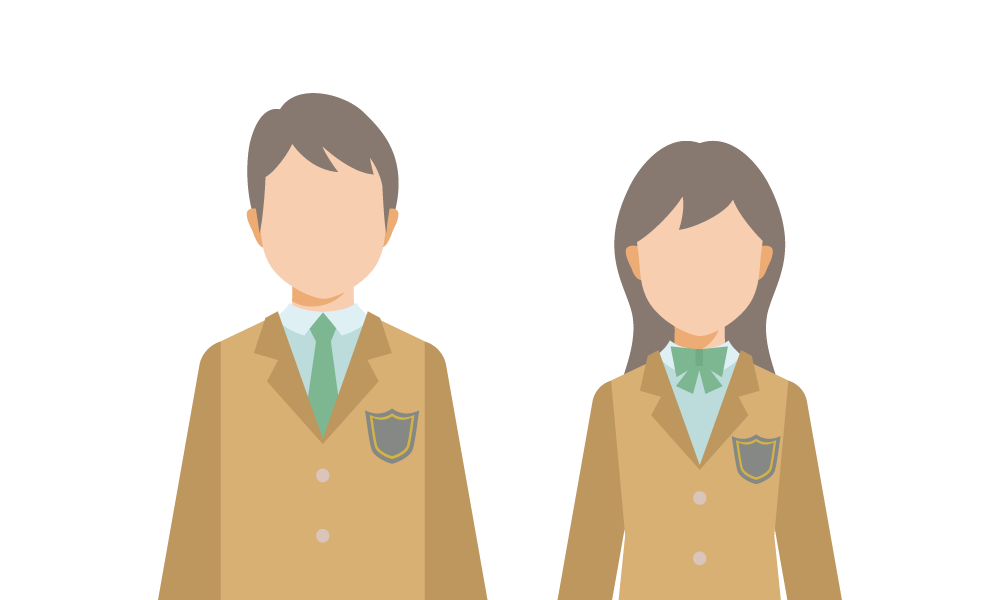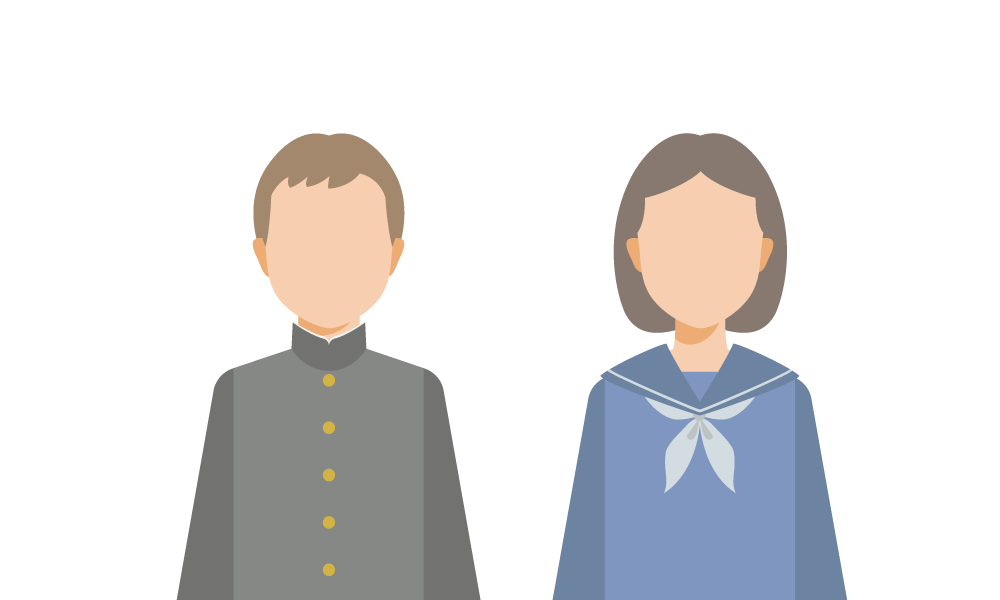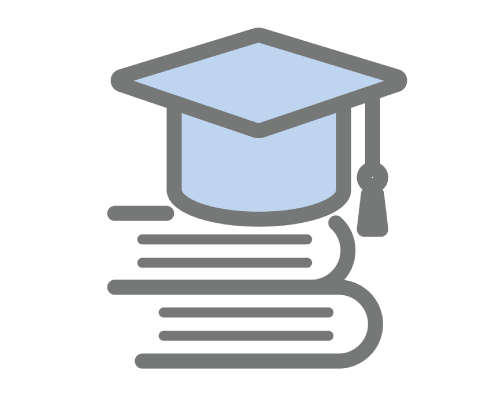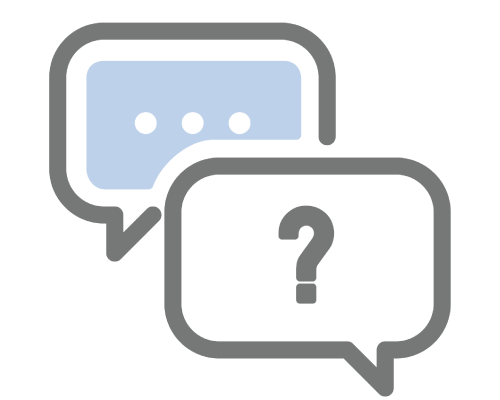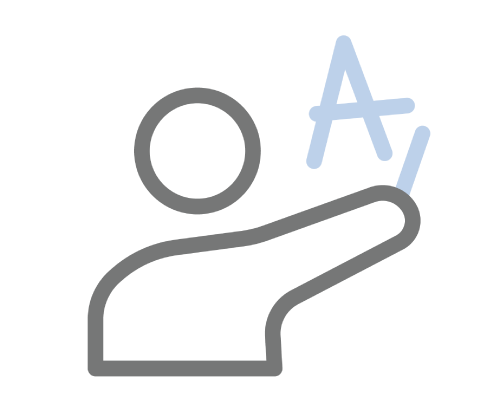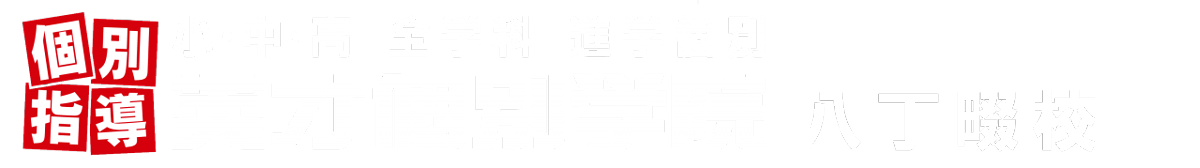ナンデモ解決!勉強ブログ
2025.09.02
箱ひげ図・度数分布は保護者世代は・・・・
こんにちは。
今回は、神奈川県の公立高校入試でも出題される 「箱ひげ図」と「度数分布」 についてお話しします。
保護者がサポートしづらい単元
箱ひげ図や度数分布は、現在の中学生が学ぶ新しい単元です。
私たち保護者世代が学生だった頃には 学習指導要領に入っておらず、全く勉強していない内容 です。
そのため保護者の方にとっては、
「見たことがない」
「説明しようにも分からない」
という状況になりやすいのです。
つまり、 家庭で最も教えにくい分野の一つ と言えます。
神奈川入試での実態
神奈川県の公立高校入試にも出題されています。
ある年度の正答率は 32.7%。
しかもこの中には「運よく答えが当たった」生徒も含まれているため、きちんと理解して正解できた生徒はもっと少ない のです。
解くカギは「代表値の整理」
箱ひげ図や度数分布を攻略するには、 代表値の整理 が不可欠です。
-
最小値(一番小さい値)
-
最大値(一番大きい値)
-
中央値(Q2)(真ん中の値)
-
第一四分位数(Q1)(下から25%の位置)
-
第三四分位数(Q3)(上から25%の位置)
-
階級値(度数分布の代表値)
これらを 実際に書き込みながら整理していく力 が得点に直結します。
室長・池田の体験談
実は私も、教室長になるまでは 箱ひげ図も度数分布も一度も解いたことがありませんでした。
完全に「生徒や保護者と同じ立場」からのスタートです。
しかし、100問ほど実際に問題を解き続けるうちに、コツをつかみ自信を持てるようになりました。
だからこそ今は、
-
「最初は分からなくて当然」
-
「慣れれば必ずできるようになる」
という気持ちを生徒と共有しながら指導しています。
未経験から学んだからこそ、生徒と同じ感情に寄り添って教えられる単元 だと強く感じています。
差がつくからこそ、得意にしよう
正答率が3割前後ということは、ここを得意にすれば一気に差をつけられる ということ。
逆に放置すると大きな失点につながります。
英才個別学院 八丁畷校では、
-
会話文から情報を整理する力
-
代表値を見抜くコツ
-
度数分布と箱ひげ図を融合させた応用問題の解き方
を 対話型授業 で一人ひとりに合わせて丁寧に教えています。
まとめ
箱ひげ図・度数分布は、保護者も生徒も「未知の領域」からのスタート。
だからこそ塾で、安心して、着実にステップアップできるように全力でサポートします。
👉 「箱ひげ図?度数分布?もう大丈夫!」と自信を持てるように、一緒に鍛えていきましょう!