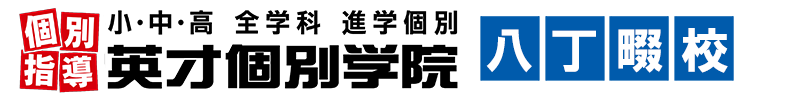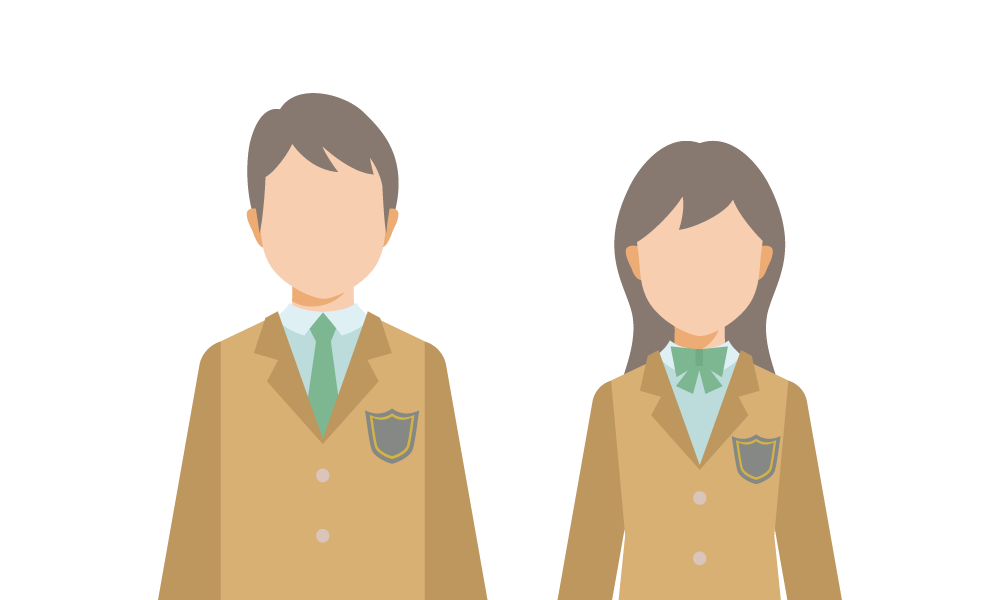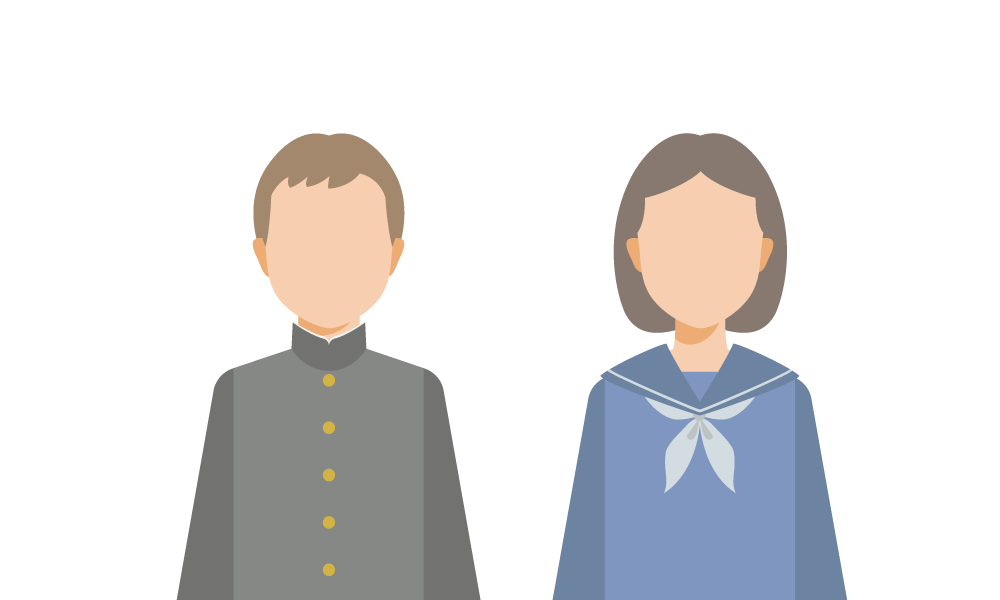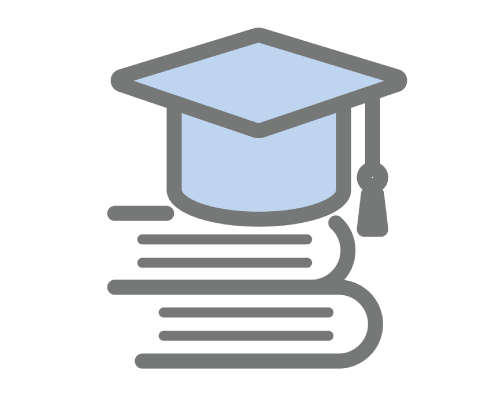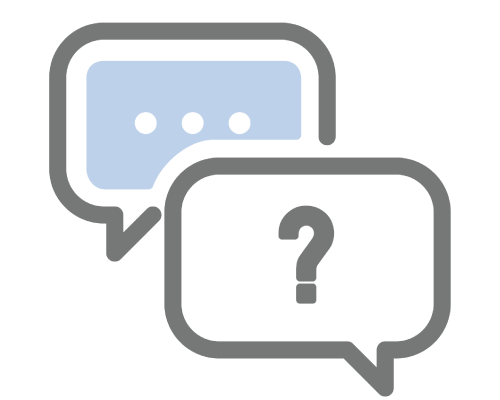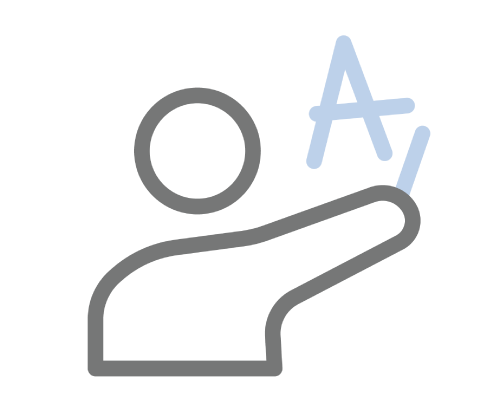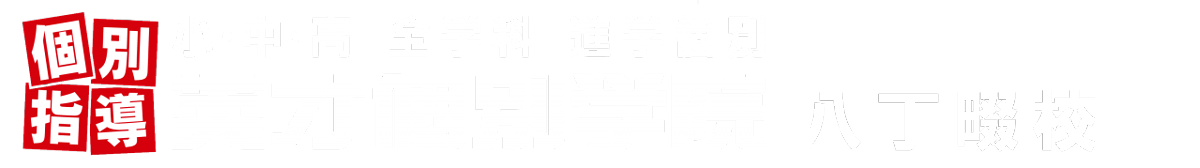ナンデモ解決!勉強ブログ
2025.08.17
共通テスト英語リーディング徹底分析!2025年の正答率から導く最適解答順序と勉強法
1. はじめに
英リーディングは「時間×処理量×正確さ」の三重苦。勝つ鍵は解く順番と時間配分です。
本記事では、2025年の公開データ(小問別正答率)をもとに大問別の平均正答率を算出し、最も点が伸びる順番と学習戦略を整理しました。
2. 大問別の配点・平均正答率(2025年度)
-
試験全体:80分/設問数は全体で約44問/配点100点
-
大問ごとの配点と平均正答率(旺文社の小問データより)
| 大問 | 配点 | 平均正答率(再計算値) | コメント |
|---|---|---|---|
| 第1問(短文) | 6 | 56.01% | 基本だが取りこぼしが出やすい |
| 第2問(複数文書照合) | 12 | 67.50% | 高正答率、確実に稼ぐ |
| 第3問(図表+短文) | 9 | 62.80% | ここも得点源 |
| 第4問(中程度の文章) | 12 | 59.61% | 中難度、読み切り勝負 |
| 第5問(長文総合) | 16 | 62.83% | 思った以上に取れる、処理速度が鍵 |
| 第6問(長文) | 12 | 41.79% | 正答率が低い、時間泥棒 |
| 第7問(長文) | 16 | 50.28% | 粘りどころ |
| 第8問(最終長文) | 17 | 47.07% | 集中力を要する締め |
※設問は「複数解答を完答で○点」など束ね採点があるため、配点と設問数は一致しません。大問別の“問題数”を一律に定義すると誤解を招くため、ここでは配点と平均正答率を軸に戦略設計をしています。
※平均正答率は、頂いた旺文社資料の小問データを集計して算出(大問1〜8の数値を上表に反映)。
3. 最適な解答順序(2025年データに基づく)
結論: 👉 第2 → 第3 → 第1 → 第4 → 第5 → 第7 → 第8 → 第6
-
第2・第3(高正答率&配点もそこそこ)で先行逃げ切り
-
第1は短文でも落としがち。集中力があるうちに回収
-
第4・第5は中盤で確実に積み増し
-
第7・第8は粘り勝負
-
第6は正答率最下位。最後回しで、残り時間に応じて“拾えるだけ拾う”
4. 時間配分の目安(80分)
-
前半(第2・第3・第1):合計25分
-
例)第2:10–11分/第3:8–9分/第1:5–6分
-
-
中盤(第4・第5):合計25分
-
例)第4:11–12分/第5:13–14分
-
-
後半(第7・第8・第6):合計30分
-
例)第7:11–12分/第8:11–12分/第6:残り(5–8分程度)
-
コツ:各大問に打ち切り時刻を設定し、超えたらいったんマークして前進。見直しフラグを立てて戻る。
5. 読解量と必要スピード
-
総語数の体感は約5,000〜6,000語(年により変動)。
-
目安はWPM 100〜120(1分100〜120語)。
-
普段から音読と多読をしてないと対応不可!!
6. 夏から伸ばす3ステップ
-
基礎(〜1か月):単語・熟語を反射レベル/文法・構文で**“時間無制限なら8割”**を作る
-
加速(2か月目):音読+多読で前から理解/段落・論理のつながりを掴む
-
実戦(3か月目〜):本番時間で演習/順番と打ち切り時刻を固定化/苦手大問は後回し訓練
7. 2021〜2025の平均点と2026年の展望
-
英リーディング平均点は概ね50〜60点帯で推移。
-
2025年は小問正答率から見ても、差がつくのは後半長文(特に第6〜8)。
-
新傾向2年目(2026)は難化寄りと読むのが妥当。
-
文章量増/根拠の取りにくい選択肢/資料+長文の融合強化…に備える。
-
8. まとめ
-
配点×正答率で考えると、**「第2→第3→第1→第4→第5→第7→第8→第6」**が最も合理的。
-
設問総数は約44問。ただし束ね採点のため、大問別“問題数”は配点と一致しません。
-
夏からでも順序×時間×省エネ読みの三点セットで、8割→9割は十分狙えます。
一緒に“点が伸びる順番”を身体に染み込ませていきましょう。迷いが消えれば、英語は伸びます!
過去問や共通テスト専用問題集を
これでもか!と30題は解く!
そして、音読を各年度最低でも30回は読む!
時間はかかるがこれが共通テスト英語を解くコツである!!