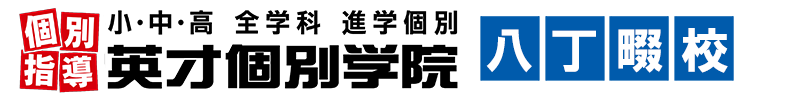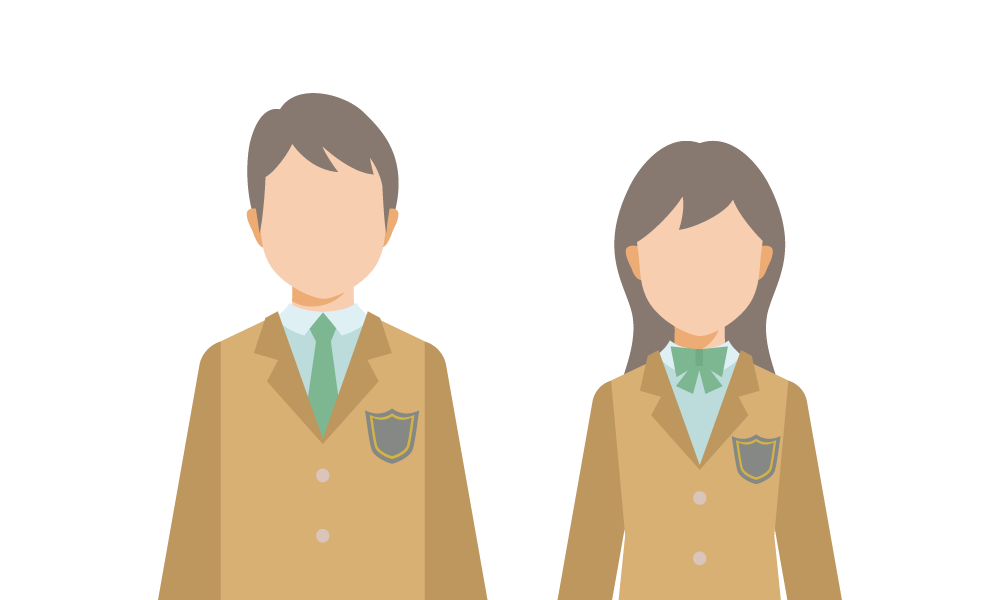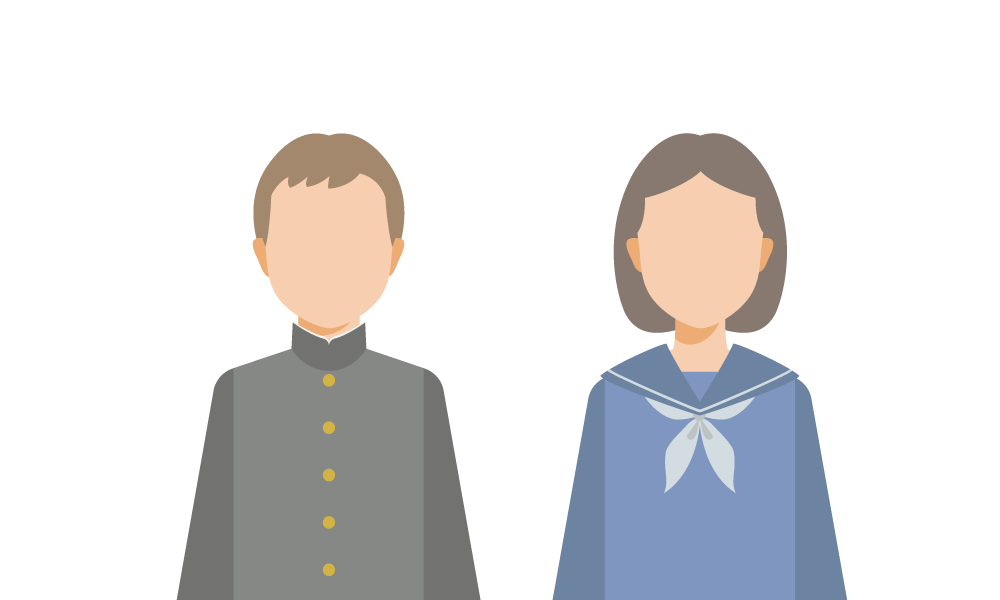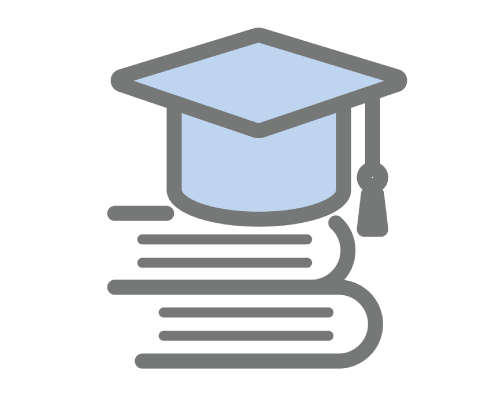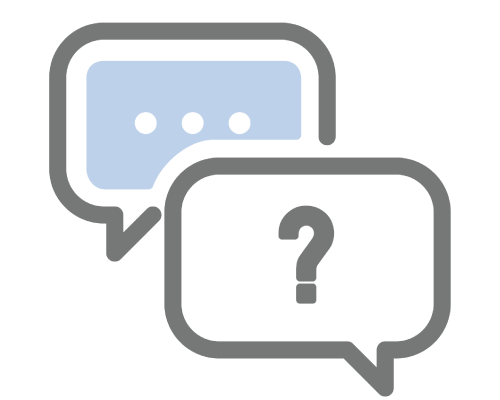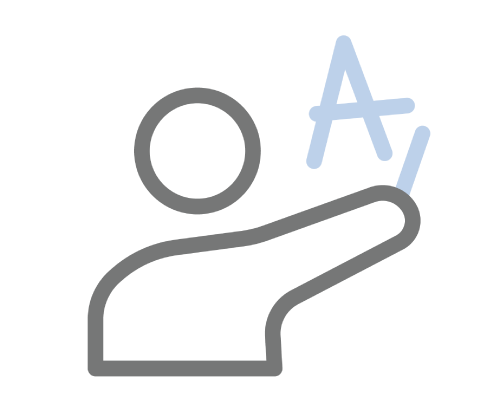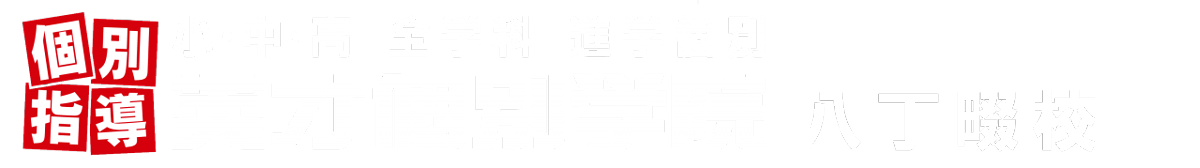ナンデモ解決!勉強ブログ
2025.08.09
歴史はなぜ公民より苦手になりやすいのか?|世界史と日本史をつなげて覚える勉強法
こんにちは!
英才個別学院 八丁畷校の池田です。
中学生の成績表を見ていると、こんなパターンがよくあります。
「歴史は苦手なのに、公民は意外と得意」
実はこれ、偶然ではありません。
今回は、なぜ歴史は公民より苦手になりやすいのか、そして歴史を克服するためのヒントをお伝えします。
歴史が苦手になりやすい理由
-
用語が昔の言葉でわかりにくい
例:六波羅探題(六波羅ってどこ?)、元禄文化(元禄っていつ?)、墾田永年私財法(なぜそんなに土地が大事?) -
人名・出来事・年号・地名など覚える量が多い
-
全体の流れを理解しないと点が取れない
-
授業で早く習うため、受験本番までに忘れやすい
-
歴史を学んでいる時、そこまで本気で勉強に熱を入れていない生徒が多い
公民が得意になりやすい理由
-
漢字を見れば意味が推測できる(三権分立、直接民主制、消費税率など)
-
現代のニュースや生活と結びついている
-
受験直前に学ぶため集中しやすい
-
出題範囲が狭く、形式も知識問題中心で得点しやすい
世界史的な「流れ」で覚える例
歴史が苦手な原因の一つは、「出来事のつながり」が見えにくいことです。
そこで、世界史の有名な流れを一つのストーリーにしてみましょう。
-
十字軍(11〜13世紀)
キリスト教徒が聖地エルサレムを奪い返すために遠征 → 東方との交易が活発に。 -
ルネサンス(14〜16世紀)
十字軍で得た知識や文化がきっかけで、古代文化の復興が進む。 -
宗教改革(16世紀前半)
カトリック教会の改革運動が起こる → 布教活動が活発に。 -
大航海時代(15〜17世紀)
新航路開拓が進み、世界中へ進出。 -
イエズス会(16世紀)
教育や医療にも力を入れるカトリック布教団体が誕生。 -
フランシスコ・ザビエル来日(1549年)
日本にキリスト教を伝え、南蛮貿易のきっかけに。
このように「点」ではなく「線」で覚えると、出来事が頭に残りやすくなります。
歴史克服のポイント
-
用語を現代の言葉に置きかえる
六波羅探題 → 「京都支部」
元禄文化 → 「江戸時代のバブル文化」 -
年表や地図で流れを視覚化する
-
世界史と日本史を関連づける
英才個別学院 八丁畷校の社会指導
当校では、歴史が苦手な生徒に対して、
-
年表×イラストでストーリー化
-
ニュースや現代社会との関連付け
-
公民は時事問題や模擬議会形式で「使える知識」に
一人ひとりに合わせたカリキュラムで、苦手科目を得意科目に変えます。
📞 英才個別学院 八丁畷校
LINE・HP・電話(044-230-0039)からお気軽にお問い合わせください。